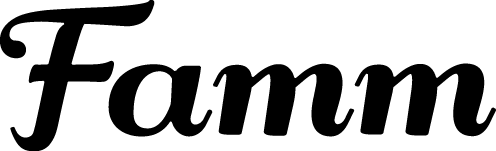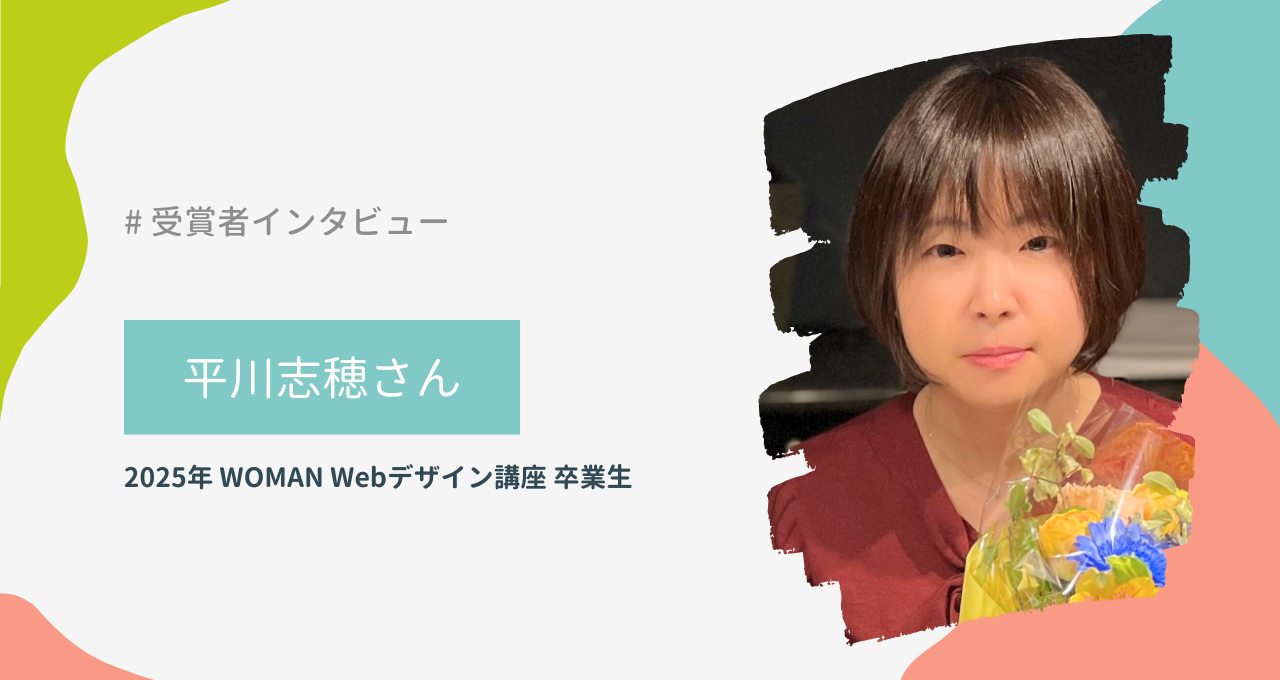平川志穂さん(WOMAN Webデザイン講座)
Fammスクールの卒業生にインタビュー
今回は2025年にWebデザイン講座を受講し、受講料無料キャンペーンに選出された平川志穂さんにお話を伺いました。
ー 受講前の仕事、家庭環境、ライフスタイルについて教えてください。
育休中で、1歳長男と0歳次男の年子を自宅保育していました。
ー 今回受講したスキルに興味を持ったきっかけは何ですか?
子ども二人を育てていくにあたって在宅で働けて、かつフリーランスとして働くことも可能な専門的な知識を身につけたいと思っていたのでWebデザインという仕事に興味を持ちました。
ー (受講前において)今回受講したスキルとPCスキルはどのような状態だったのか教えてください。
Webデザインに関しての知識は何もなく、どのような仕事かも詳しくは知りませんでした。
PCスキルについては仕事で日常的に使用していたので必要最低限の知識は持っていましたし、扱うことには慣れていたと思います。
ー スクールに通うことへの不安はありましたか?(時間、費用、スキル習得など)
子どもを二人自宅保育しているので講座にきちんと参加できるのか、学習をするためのまとまった時間は取れるのかと不安でした。
また、費用面も決して安い金額ではないので、金額に見合ったものが得られるのかという不安も持っていたと思います。
ー 講座内容で印象に残っていること、役に立ったことは何ですか?
全く何も知らない状態でデザインを学び始めたので、デザインに関する学習は全て印象に残っています。
今まで何気なく見ていたウェブ広告や街中で見かける広告、チラシなど全て新しい視点で見られるようになって楽しくなったのを覚えています。また、初めて触るPhotoshopもこんなことができるのかと驚きの連続でした。
HTML/CSSの講座でもどんなWebサイトがユーザーにとって操作しやすいか、ページ内容を読んでもらえるかなど、細かくこだわって作られていることを知りました。
ー 「学習」と「仕事(家事、育児も含む)」の両立について、工夫したことを教えてください。
日中は自宅保育のためほとんど学習の時間は取れそうになかったので、寝かしつけの終わった夜にまとめて学習時間を取ろうと割り切っていました。
日中何もできなくても焦らないように、子どもたちがお昼寝をしている間に少しでも参考書籍を読めたらラッキーと思えるくらいのマインドでいました。
どうしても時間が必要な時は夫に相談して数時間だけ子どもを見てもらう日もありました。
ー スクール卒業後の現在の活動状況について教えてください。
クリエイター同士のコミュニティに入り、そこで行われるコンペや添削会、セミナーに参加して新しい知識や技術を身につけています。
コミュニティ外のコンペやセミナーにも積極的に参加して学習する習慣が途切れないことを意識しています。
また、Xで発信を行うことも続けていて同じクリエイターとして活動されている方やスクールの同期と情報交換を通して交流しています。
ー 今後、目指していく働き方について教えてください。
今年中に仕事復帰する予定ではありますが、小さな子を二人抱えながらなのでおそらく時短での復帰となるかと思います。
そのためこれまで得た知識を生かしてまずは副業としてWebデザイナーのお仕事をしたいと思っています。
子どもにあまり手がかからなくなってくる頃にはしっかりと収入を得て、本業は辞めフリーランスとして本格的にWebデザイナーとして活躍していきたいと考えています。
ー Fammスクールをおすすめするポイントを教えてください。
仕事や育児で時間を作ることが難しい方でも、1ヶ月という短期集中コースで基本的なスキルを身につけることができ、受講中や卒業後のサポートも充実している点が魅力的だと思います。
また、クリエイターとして活動するために必要なSNSでの発信も、受講料無料キャンペーンの一環として毎日触れる習慣が身につくため、とても良い点だと思います。
ー 受講を迷っている方、または既に受講を予定している方に向けてアドバイスをお願いします。
全5回の講座では主に基本的なことを学びますが、それだけですぐにお仕事として活動することは難しいです。
これはどのスクールに通っても同じだと思いますが、自分でしっかりと予習や復習をし、学習時間を確保することが重要です。
そのため、学習スケジュールを意識的に組むことをおすすめします。
また、副業やフリーランスとして活動していくためには、自分で積極的に情報を集めることが大切です。
そのため、クラスメイトや同期、講師の方とのコミュニケーションを取り、交流を通して横のつながりを作っておくことも受講前から意識しておくべきだと思います。